財団スタッフDIARY
0年0月の記事一覧
【FORUM PRESSレポーター】「第3回ワンコインコンサート『Lune』」
「FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。
市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。
今回は、2018年9月22日(土)に開催された、
【第3回ワンコインコンサート「Lune」】を、2人がレポート!

 Report330【愛のかたちを音で奏で…】 川島寿美枝
Report330【愛のかたちを音で奏で…】 川島寿美枝
若手音楽家支援事業であるワンコインコンサート。3組目の「Lune」は結成して4年目。地元春日井出身のクラリネットの伊藤美佳里さん、サクソフォンの足立真里那さんという2人のミューズと、守護神の如く華麗なピアノで演奏を盛り上げる耕作彦充さん。まだ若い3人ですが、息の合った演奏、そしてトークに魅了されました。今回<恋するクラシック>と銘打って、愛のかたちを音で表現。
クラシックの名曲の中にはまだ馴染みのない曲もありましたが、ミューズたちは埋もれた名曲を掘り出して、沢山の人に知ってもらおうと演奏活動を続けているそうです。一曲ごとに紹介があり、その曲の背景や時代を感じ取りながら、3つの楽器のハーモニーにひき込まれました。この3つの楽器の楽譜は少なく、伊藤さん、足立さんはトリオのために他の楽器の楽譜を編曲し直しているというお話をお聞きして、演奏家の苦労を知りました。これからの3人の活躍が楽しみです。
 Report331【あの名曲は、単に半音下がるだけ!?】 與後玲子
Report331【あの名曲は、単に半音下がるだけ!?】 與後玲子
当初は、クラリネットとサクソフォンのアンサンブルとして活動を始め、後にピアノを加えて「Lune」を結成。若い二人の女性が醸し出す優しく、かつ繊細なクラリネットとサクソフォンの音色。そして男性の包容力のあるピアノが要となって、一つの芸術を作り出していました。前半には、「バレエ音楽『恋は魔術師』より」と「美しき夕暮れ」をクラリネット、そして「オーベルニュの歌」をサクソフォンのソロで演奏。それぞれの音色の違いや演奏者の個性が際立ち興味深いものでした。後半には、馴染みのある映画音楽のメドレー等に加え、「カルメン幻想曲」よりハバネラを披露。あのとても有名で個性的なメロディーは、実は何と半音ずつ単に下がっているだけということの説明を受けびっくり。実際に演奏を聴いてみて、目から鱗が落ちた瞬間でした。音を奏でることの奥深さと面白さを感じたコンサートでした。
【FORUM PRESSレポーター】「物語付きクラシックコンサート アラジンと魔法のランプ」
「FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。
市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。
今回は、2018年8月25日(土)に開催された、
日生劇場ファミリーフェスティヴァル2018
【物語付きクラシックコンサート アラジンと魔法のランプ】を、4人がレポート!

Report326【音楽は素晴らしき魔法】 のぐちりえ
こういう子ども向けのコンサートはもっと頻繁に開かれるべき!そう感じました。
カラフルな舞台で、ピアノが苦手なアラジン、コミカルなランプの精、お婿さん探しをするお姫様と王様、そして悪い魔法使いが、歌い踊りミュージカル仕立てで話が進みます。大人でも面白く、一緒に観に行った娘もがっつりと心を掴まれているようでした。音楽の授業で習った耳馴染みのある曲が流れ、作曲家おもしろクイズもあり、小学校高学年にはドンピシャの内容だったようです。
音楽、そして演奏とは素晴らしいですね。音色が綺麗なのは言うまでもなく、その曲調によって喜怒哀楽を表現したり、あるいはその曲を聞くことによって鼓舞されたり癒されたり。そんな魔法のような力を持つ音楽に、たくさん触れて好きになってもらいたい、という願いが込められたコンサートだったように思います。多感な子供時代だからこそ、このような良質なコンサートにたくさん足を運べるといいですね。
 Report327【真夏の魔法コンサート】 川島寿美枝
Report327【真夏の魔法コンサート】 川島寿美枝
会場に入ると、沢山の親子連れで賑わい、子どもたちの声がホールに響き渡っています。ステージ上には白いオーガンジーとエキゾチックな柄の緞帳が下がり、ファンタジーにあふれています。大人も子どもも楽しめるクラシックコンサートとは、どんなものかと期待が高まります。
アラジンと魔法のランプの精がストーリーの案内人です。オーケストラの演奏が始まると、どこかで聞いたことのある楽曲が次々と飛び出します。オペラのアリアあり、ダンスありで、子どもたちの目はもう舞台にくぎ付けです。魔法使いドロローソのピアノを担当する宮谷理香さんの力強い演奏に、誰もが聴き惚れてしまいました。ショパン国際ピアノコンクール入賞者と聞き、さすがと思いました。子どもたちが音楽に親しみがもてる仕掛けが沢山出てきて、最後まで楽しめ、またこの次も見てみたいと思ったことでしょう。
Report328【小さな子どもたちの笑顔】 中林由紀江
夏休み終盤、土曜日の夕方、子ども連れの家族が目立ち賑わう会場に鑑賞にいきました。手渡された可愛い絵付きのパンフレットには、演奏曲全てに、作曲家加藤昌則さんが書いた分かり易い解説があり、周りの子ども達も始まる前から大人に読んでもらったりして、ワクワク感がいっぱいでした。始まるとキャスト、オーケストラ、そして私たち観客もいつの間にか物語の世界に入り込んでいました。宝塚の男役のような格好良い「魔法使い」はピアノも上手で、天は二物を与えるのだなと思っていたら、最後の紹介で後ろから可愛い「魔法使い」が飛び出してきて、俳優とピアノ奏者の二人で一役だったことにビックリしました。歌もオーケストラもピアノの演奏も全て一流で、文字通り大人も子どもも楽しめるコンサートでした。歴史上の偉大な作曲家のことも演奏付きで楽しく紹介され、勉強になった夏の日でした。来年は愛知県芸術劇場で開催される予定とのことなので、次回は孫と一緒に鑑賞しようと思いました。
 Report329【感動がいっぱい!みんな、見に来て】 マエジマキョウコ
Report329【感動がいっぱい!みんな、見に来て】 マエジマキョウコ
はじめの一音からひきこまれました。「ファミリーフェスティヴァル」だから「子どもだましなんじゃない?」という先入観はイイ意味で思い切り裏切られました。
アラジンとランプの精がお姫様を助けるためにピアノを練習する、というお話。オペラ「ドン・ジョヴァンニ」や「ロミオとジュリエット」など名曲が並ぶなかに、ピアノを前にもんもんとするアラジンが、基礎練習でよく使われる曲を弾く場面もあって面白かった!
その音域の広さと演奏の多様性から「ピアノは小さなオーケストラ」といわれていることは知っていましたが、これほどの迫力と豊かな表現力があるとは!ピアノの音にほんと魅せられました。さらにひろがるオーケストラもすごい表現力。それに加えて力強い歌声が……コレもまた上乗せされるとすごいっ!クオリティーは超一流。ほんと楽しかった!楽しいのが音楽ですよね♪ 心に届く素晴らしい音楽会でした。
【FORUM PRESSレポーター】「花形狂言2018 真夏の狂言大作戦!」
「FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。
市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。
今回は、2018年8月19日(日)に開催された、
【花形狂言2018 真夏の狂言大作戦!】を、3人がレポート!
上杉遥.jpg)
(c)上杉遥
Report323【狂言はたえず】 宮川あけみ
この夏も、ここ春日井に登場した狂言ユニット「HANAGATA」。どんな笑いを見せてくれるのか、大いに期待して席に。初めに、メンバーの茂山逸平さんから狂言とは “~のつもり” の積み重ねであるとの解説がありました。さらに、突っ込みどころがあっても突っ込まない(笑)、その場の想像をしてほしいとも言っていました。観客であるのと同時に舞台での景色の一部になる、そう感じました。演目は古典と新作合わせて5作品。そのなかでも、グッと身を乗り出して聞いたのは、新作「伝統はたえた」。奥義を教えるからと師匠に呼ばれた弟子。しかし、肝心の師匠は物忘れが進んでいる様子。繰り返す話にたまりかねた弟子が師匠の頭をポカッと叩く度にどんどん忘れ、遂には奥義も消えてしまうというオチでした。会話のテンポがよく、引き込まれました。そして、こちらも弟子の気持ちで師匠の言葉を待ち、ヤキモキする。この人間くさいオチが、狂言の面白さだと思いました。
Report324【魅力いっぱいの花形狂言】 田本莞奈
古典から最新作まで披露された「花形狂言2018」。
全部で5演目でしたが、どの演目も他の演目のネタを取り入れて会場をもりあげていました。1つ目の演目は、古典の「蝸牛」。太郎冠者は、かたつむりを探しに、竹やぶへ行きます。すると、竹やぶにいた山伏が、自分がかたつむりだとうそをついて、はやし立てる演目です。プログラムにはかいてありませんでしたが、演目と演目の間に、少しの間、落語がありました。3つ目の演目は、最新作「すなの、しろ」。この演目では、春日井名物サボテンを使った謎かけもありました。目からビームをだしたり、ライトの色がかわったりするシーンもありました。最新作だからこそ、現代的なものを取り入れることができると思いました。
楽しかったです。
Report325【花形狂言は奇想天外】 こじまみつこ
茂山逸平さんが初めに、狂言とは「オジサン達が大きな声で大げさに」「道具を使わずすべて言葉で表現」するものだと、冗談交じりに話されました。
古典の「蝸牛」。山伏が大きな声で自己紹介し、大げさな身振りで動き回ります。長寿の源・蝸牛を探す主と家来は、自分を蝸牛だと言う山伏に、ころっと騙されて「でーんでんむしむし」と皆で歌いだすのです。意外にわかりやすく、面白い!
最新作「すなの、しろ」。恋人の浮気に怒り狂った女が、突然アニメキャラクターの巨人に変身。ビームを発したり足で踏みつけたり、街を破壊しつくします。ハチャメチャな!と、思いながらも、アニメと狂言の世界観が上手くマッチしていました。恋人に許してもらいたい男は、「側転をしろ」「なぞかけをしろ」等、周りのものに無理難題を吹っ掛け、やりたい放題です。
満員の会場は拍手と笑いで溢れかえり、子供も年配の方も、茂山家ならではの狂言の世界に満悦していました。狂言って楽しいですね。
【FORUM PRESSレポーター】「親子で挑戦!謎解きゲーム in 市民会館」
「FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。
市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。
今回は、2018年8月15日(水)に開催された、
【親子で挑戦!謎解きゲーム in 市民会館】を、4人がレポート!

Report319【市民会館について知るツアー】 田本莞奈
夏休みに親子で参加してもらい、春日井市民会館について知ってほしいという目的でおこなわれた「かすがい文化フェスティバル『親子で挑戦!謎解きゲームin市民会館』」。
このツアーでは、いくつかの謎をといていきました。ふだんは、なかなか、見たり入ったりできない楽屋や、音響室などの見学もできました。このツアーの1問目は、ロビーにかくされている文字を探して、言葉を作るという謎。答えは「らせんかいだん」でした。他にも、客席にかくされている文字を探したり、楽屋にあるざぶとんやイスの数などを紙にかいて、謎をといていきました。音響室では、いくつかのレバーがあり、そこにかいてある絵で、種類が同じだと思う物のレバーをあげ、曲がながれるという謎ときでした。舞台に立つこともでき、写真撮影もできました。
ふだんは、なかなか、見たり入ったりできないようなところも見学することができ、よかったです。楽しかったです。
Report320【謎解きで劇場の中を探検!】 山田真穂
劇場で謎解きをするのは初めて!まずはロビーで文字探し。チラシのラックやベンチの裏などに文字が隠されていて、見つけるのになかなか苦労しました。なんとか「らせんかいだん」を導き出し、螺旋階段を上がってピアノのある楽屋へ。渡されたファイルの謎を解いて、ピアノの音を出すと、「正解~!」とヴァイオリン弾きのお姉さんが、美しい演奏で次の部屋へ案内してくれました。またまた階段を上がり音響室へ。ここではミキサーでの6つのボリューム操作を体験し、次は客席へ。席に貼ってある「がくや」の文字を発見して楽屋へ行き、座布団と椅子の数を数えて、その数字の暗号で宝箱を開けると、最後の挑戦状が!舞台袖へ行き、相方に挑戦状の紙を見ながら機械を操作してもらっている間に、私は舞台の真ん中へ。すると照明が私を照らし、ミラーボールが後ろでキラキラ輝いて回り、目の前に「クリアおめでとう」の看板が!最後は看板を背景に記念撮影をして、非常に楽しいひと時でした。
 Report321【会館裏側を謎解き探検】 紀瑠美
Report321【会館裏側を謎解き探検】 紀瑠美
「春日井市民会館を知ってほしい」という、かすがい市民文化財団スタッフの願いで、初めて企画された市民会館探検ツアー。より楽しんでもらうために工夫を凝らし、会館全体を使った「謎ときゲーム」をしかけました。応募多数のため抽選で選ばれた30家族85人が、5分ごとにスタートしていきました。普段は入れない会館裏側を探検できるドキドキ感と、謎をとくワクワク感があいまって、参加者は大いに盛り上がっていました。ロビーやたくさんの楽屋、客席や音響室で謎をいていき、最後はステージへ。驚きの演出で、とびきり笑顔の写真が撮れました。会館を知り尽くした財団スタッフさんたち。企画も当日運営も、参加者を喜ばせるための、嬉しい演出はさすがでした。子どもも大人も楽しめる夏休み恒例イベントになりそうで、来年からも楽しみです。音響室と舞台では、機械の操作もでき興味深かったので、じっくりと体験できるようなイベントも、ぜひ企画してほしいです。
Report322【宝物探しの冒険へ出発!!】 山本祐美加
夏休みに親子で体験できるという、初めての謎解き体験。場所は、なんと春日井市民会館。えー!!この場所でどんな謎解きするの?と気持ちは、期待と少しの??でいっぱいでした。
一つだけでなく、次から次へ解かなければいけない謎。大人の私も夢中になって、取り組みました。なるほど!こういうことか!と答えが分かるたびに喜びの声をあげてしまうほどでした。自分の子どもにかっこいい姿を見せたいと感じたお父さん、お母さんも多かったのではないでしょうか。ゴールしたときの感動と達成感は、自分でも驚きでした。
いつもは静かに鑑賞するというイメージの春日井市民会館ですが、その場所がのとびきりの冒険の舞台になるとは想像すらできず、いい意味で期待を裏切られました。第2弾も期待したい!最後はそんなふうに思えました。大人も子どもも楽しめる、ドキドキ・ワクワク最高の謎解きアドベンチャーでした。
【FORUM PRESSレポーター】「第88回かすがい芸術劇場 人形劇団むすび座『父と暮せば』」
「FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。
市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。
今回は、2018年8月10日(金)に開催された、
【第88回かすがい芸術劇場「人形劇団むすび座『父と暮せば』」】を、7人がレポート!
FORUM PRESSvol.88にもレポートを掲載しています。Report310はコチラからPDFでお読みいただけます。

Report312【8月の恒例行事として、子にも孫にも伝えていきたい人形劇鑑賞】
中林由紀江
お盆前の汗ばむ夜に、井上ひさし作の戯曲「父と暮せば」の人形劇を観に行きました。名古屋の老舗人形劇団むすび座の公演です。モノである人形に魂が吹き込まれたような生き生きとした動き、心地良いリズムを刻む広島弁の言葉。終戦まぎわの広島に自分が実際いるような気持ちでした。原爆投下時の人々の生々しい苦悩や葛藤が目に浮かび、いつしか周りの観客と一緒に涙を流す自分がいました。「この作品を大切に育てて届けて行きたい」という気持ちで7年公演を続けておられるそうです。終戦記念日のある8月のこの時期に観賞できて良かった。毎年この時期に見続けたい作品です。子供にも孫にも見せてあげたいので、ずうっと続けていってほしい。公演後、観客に演者の方が人形を触らせてくださり、丁寧に説明してくださる真摯な姿勢をみて明日から頑張ろうと思い、背筋がピンとして元気をもらった夜でした。
Report313【この夏に考える、原爆と親子の絆】 山田真穂
広島の原爆投下日の少し後に行われた今回の公演。会場に入るとセミの鳴き声が響いていました。被爆がきっかけで自分の心を閉じてしまった美津江。幽霊となった父との広島弁での日常会話をユーモアのある笑いを交えながらには笑いが交ざるものの、「生き残っていることが不自然」「私は幸せになってはいけない」と苦しみながら生きる様子を見て、美津江の辛さが伝わってきました。
最後の父との原爆時の死別のシーンでは、会場全体がしんみりした雰囲気に包まれました。ハンカチを押さえながら涙を流す人や鼻をすする音。私も目に涙を浮かべずにはいられませんでした。また、人形を操る出演者の渾身の演技にも心を打たれました。原爆の経験がない私でも、太陽2個分の温度というセリフ、お地蔵さんの焼け焦げた顔などから当時の様子を想像できました。父を置き去りに逃げたことをずっと引きずっている美津江に対し、自分の分まで堂々と前を向いて生きてくれという父の強いメッセージが心に残った真夏の日の夜でした。
Report314【いのちをつたえる物語】 こじまみつこ
蝉しぐれが止むと、突然の雷鳴。そして父と娘の物語は始まります。原爆によって亡くなり、幽霊となって現れた父親。父親を助けられなかったことを悔い、幸せへの心を閉じた娘。
父親と娘、2人の思いを2人の人形遣いと2人の話し手が演じます。
2人で人形を操ったり、言葉のみで演じたり。4人の変幻自在の動きに、話し手に視線が行き過ぎて慌てて人形を見たり、反対に人形に集中しすぎて、話し手の言葉を聞き逃したり。身を乗り出すようにして4人の動きと言葉を追いました。広島弁で繰り出す言葉は、柔らかく身に染みわたる。父と娘の思いがにじみます。
表情のない人形は、怒り・悲しみ・喜びの言葉によって生き生きと動き、様々な表情をみせてくれます。小さな笠をかぶせた裸電球や手作りで作られた小道具は、自分が小さい頃の暮らしを思い出させます。
井上ひさしの戯曲と人形劇団むすび座の人形たち・話し手たちによる「今を生きることの大切さ」を教えてくれる物語でした。
 Report315【過ぎたことにしてはいけないお芝居がここにある!】
Report315【過ぎたことにしてはいけないお芝居がここにある!】
マエジマキョウコ
「おとったん、ありがとありました」
『父と暮せば』のラストシーン。「原爆で、『死ぬのがあたりまえ』のなかで生き残った罪悪感」をやっとふっきった娘・美津江が、やわらかい広島弁で、成仏して消えていった父・竹造に頭をさげます。その姿が平成の平和に慣れきった私の心に深く突き刺さりました。
原爆投下から3年。広島弁でつむがれる父娘のやりとりはあたたかく、通じきれない思いはもどかしく、その情に共感することしきり。親子というのはここまで互いを思いやれるものなのかと感じ入りました。
人形劇団むすび座のお芝居は、人形劇ならではの宙に浮いたり突然現れたりという演出もさることながら、4人の俳優が人形を操り、セリフを朗読し、かと思えば全員で会話をぶつけ合う……。意表をついた演出に圧倒されました。
このお芝居を見て「あなたはなぜ生きているの」この言葉を胸に刻みつけて生きてゆかねばと思わされました。
心に残るお芝居でした。ほんとうに「ありがとありました」。
 Report316【大人も感動!人形劇】 紀瑠美
Report316【大人も感動!人形劇】 紀瑠美
人形劇団むすび座の「父と暮せば」は、見本のないところから劇団員の創意工夫で創り上げ、7年にわたる再演を重ね、大切に育てられてきました。無駄のない成熟した舞台は、緊張感を高めたかと思うと、絶妙なタイミングでコミカルなシーンを織り交ぜ、観客の涙と笑いを誘いながら展開していきました。
人形劇「父と暮せば」は一般的な「人形劇」とは異なり、人間は「黒子」にはなりません。人形の遣い手、セリフ担当、役者と、その役割を変化させながら舞台上に存在します。人形劇に朗読劇と演劇を重ね合わせたようでした。3体の人形と4人の役者は、融合したり、離れたり、入れ替わったりしながら自在に物語を紡いでいきます。人形の動きは生きているようでした。場所は、ヒロイン・美津江の家の居間。わずかな時間の暗転で戦争中の舞台セットへの変化も見事でした。
公演後は、人形や舞台セットを見学する時間があり、たくさんの観客が熱心に写真を撮ったり、質問したりしていました。
 Report317【井上ひさしの世界観が人形劇で!】 阪井真佐子
Report317【井上ひさしの世界観が人形劇で!】 阪井真佐子
あの井上ひさしの戯曲『父と暮せば』が人形劇になりました。もともと二人芝居の戯曲、しかも背景の変化もないひたすら内容で勝負しなければならない舞台を、人形劇団むすび座は一体どんな味付けをし肉付けして私たち観客の心を魅了してくれるのか、そこが一番の楽しみでした。人形は二体。共に表情がありません。ところが、四人の俳優が、その二体に見事に命を吹き込んだのです。まるで文楽の人形遣いにも似た人形の操り方。美津江がお茶を載せてお盆で運ぶ仕種や包丁で野菜を切るシーンなどは、俳優が人形に乗り移ったかのように自然でした。人形に表情がない分、それをセリフで俳優が人形の表情を私たちに伝えてくれるのです。一つ一つのセリフの長さも、四人で演じ分けることで新鮮となり、人形劇だからこそできる醍醐味も味わえました。井上ひさしが後世に伝えたいメッセージ「生きる」も、人形と俳優たちによって、涙と共に確実に届いたように思います。
Report318【俳優さんもみえる人形劇】 田本莞奈
1948年夏の広島を舞台に作られた「父と暮せば」。俳優さん4人が、人形を動かしたり、セリフを言ったりしました。
開演前、会場では、虫の鳴き声がしていました。俳優さんが、人形を動かしたり、セリフを言ったりしているところもみることができ、俳優さんのひょうじょうがかわっていることもわかりました。「父と暮せば」は、父の竹造さんやむすめの美津江さんもでてきます。いちばんはじめのセリフは「おとったん、こわーい!」。美津江さんのセリフです。そして「おとったん、ありがとありました。」という美津江さんのセリフでおわりです。
私は、戦争がとてもこわいと思いました。たくさんの方がかなしんで、つらいおもいをして、たいへんだったと思います。「父と暮せば」をみて、私は、こわいと思いました。戦争は、もうおこってほしくないです。
【FORUM PRESSレポーター】「松竹大歌舞伎」
FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。
市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。
今回は、2018年7月16日(月・祝)に開催された、【松竹大歌舞伎】を、2人がレポート!
FORUM PRESSvol.88にもレポートを掲載しています。Report308はコチラからPDFでお読みいただけます。

 Report309【百聞は一見に如かず】 與後玲子
Report309【百聞は一見に如かず】 與後玲子
一歩会場に入ると、着物や浴衣を着たお客さんの姿が。歌舞伎は、そのセリフや所作が現代の私達とは少しかけ離れていて、物語を理解するのは難しいような気がしていました。しかし今回は、イヤホンガイドを借り、演目のあらすじ、見どころ、背景等を知ったことで、より深く、面白く鑑賞することができました。解説によって、登場人物の心の動きがわかり、役者さんの熱い演技が、より輝いて見えるようになりました。最初は、長い布を巧みに使っての、楽しい趣向に富んだ「近江のお兼」。2番目は、歌舞伎ならではの豪華な衣裳、独特な立ち振舞いを楽しめる「御所五郎蔵」。 最後は、高下駄を履いてタップを踏み鳴らす「高坏」。狂言のように明るく楽しい作品で、場内で笑いが巻き起こりました。尾上菊之助さん始め、其々見事な演技に拍手喝采でした。

Report310【楽しかった「松竹大歌舞伎」】 田本莞奈
春日井市民会館で、34回目の「松竹大歌舞伎」が開催されました。
私は「青少年サポートプログラム」を利用して、歌舞伎をみました。「青少年サポートプログラム」は、小中高生が対象で、500円で公演をみることができ、公演前のミニ講座や、イヤホンガイドの無料貸し出しもありました。ミニ講座では、職員の方が写真やイラストをみせながら、説明してくださいました。
最初の演目は「近江のお兼」。私は、日本舞踊を習っていて、「近江のお兼」を踊ったことがあるので、みることができ、よかったです。二つ目は「御所五郎蔵」。最近流行っている言葉も、台詞にはいっていて、もりあがりました。三つ目は「高坏」。次郎冠者がお酒を飲んで、高足をはいて、タップダンスを踊るのです。最後には、大名某と太郎冠者も一緒になって、タップダンスを踊ります。
「松竹大歌舞伎」楽しかったです。
【FORUM PRESSレポーター】「山下洋輔スペシャル・ビッグバンド・コンサート2018」
「FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。
市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。
今回は、2018年6月24日(日)に開催された、
【山下洋輔スペシャル・ビッグバンド・コンサート2018】を、3人がレポート!

(C) Jimmy & Dena Katz
Report305【スペシャルな夕べ】 澤田佳奈子
ステージに黒のフォーマルで決めた15人が登場。最後に白いスーツの山下洋輔さんが現れると、拍手は一段と大きくなりました。山下さんがトップミュージシャンたちに呼びかけ、2006年に結成されたビッグバンド。2年に一度の春日井公演には、贅沢でパワフルな音色と空間を楽しみにしているリピーターが多いようです。ステージ向かって右側のトランペットやトロンボーンなどの管楽器、中央のドラムとベース、そして左側のピアノの山下さん。豪華な顔ぶれに、期待が高まりました。スペシャリスト達のあうんの呼吸による演奏が、ジャズを知らない私を、一瞬にしてジャジーな空間へ引き込みます。『極東組曲』や『ボレロ』(筒井康隆さんによれば“脱臼したボレロ”)の1部、そして『組曲 山下洋輔トリオ』の2部構成。ピアノが体の一部と化した山下さんが、どのシーンでも、ビッグバンドに笑顔を送りながら演奏する様子が、とても印象的でした。
 Report306【魂を揺さぶるジャズサウンド】 阪井真佐子
Report306【魂を揺さぶるジャズサウンド】 阪井真佐子
山下洋輔氏が、聖地と呼ぶ春日井でのコンサートは、2008年から隔年で開催され、今年でなんと6回目。白いスーツで登場した華奢な山下氏は、70歳をゆうに超えているにも拘らず、彼が弾くピアノは精力的で、魂を揺さぶる力強さに溢れており、聴いている者たちを痺れさせます。ひじから手首を使って、豪快に鍵盤を打ち鳴らす“ひじ打ち”も大迫力!お得意のひじを前に突き出し「これで50年」とおっしゃった、山下氏のお茶目ぶりに人柄が伺えました。“脱臼したボレロ”と評されるほど、斬新なアレンジが施された『ボレロ』は、クラッシックを骨だけ残し、まさかここまで自由に肉付けできるものかと、驚嘆せざるを得ない圧巻のステージ。さらに、伝説トリオの名曲が、組曲として甦った『組曲 山下洋輔トリオ』は、山下ファンのみならず、ジャズファンのハートを完全にノックアウトしたようです。聖地春日井で初披露となったこの曲は、私たちにとって最高のプレゼントになりました。
 Report307【至福のジャズの時間】 こじまみつこ
Report307【至福のジャズの時間】 こじまみつこ
ジャズ界の巨匠、山下洋輔さんが春日井にやって来ました。トランペット×4、トロンボーン×4、サキソフォン×5、コントラバスにドラムの、トップミュージシャンたちを引き連れて。曲目はD・エリントンの『極東組曲』、ラベルの『ボレロ』、そして『組曲 山下洋輔トリオ』。
指揮者はいないのに、阿吽の呼吸で演奏は始まります。「皆が勝手に演奏している」と山下さんは言いながらも、まとまりは抜群。代わる代わる舞台中央に立ち、力いっぱいアドリブソロを演奏する奏者たちに、客席からの大きな拍手が鳴り止みません。
ピアノに向かう山下さんは楽しそう。軽い調子の指さばきから、肘まで使った華麗な演奏。鍵盤全部を使ったダイナミックな演奏も。
一人ひとりの楽器から飛び出した音が、会場内を自由に駆け回るようです。観客は拍子をとりながら、リズムに体を自然にゆだねます。ジャズって面白い。ジャズって心地よい。ワクワクしてきます。
終演後、家族や友人と談笑しながら帰っていく人の顔には、笑顔が溢れていました。
インターン佐藤の研修報告レポート こだわりの「FORUM PRESS」
皆さんはじめまして。
この度、文化庁の国内専門家フェローシップ制度の一環で、(公財)かすがい市民文化財団にお世話になっています、佐藤拓矢と申します。
この制度は、文化事業に関わる人材の育成を目的とした研修制度です。私は普段、東京に所在する伝統芸能企画制作オフィス・古典空間という企業で働いています。
私たちの活動の場は劇場がとても多く、春日井にて文化事業の運営体制や広報戦略、民間企業との連携手段などのノウハウを学びに参りました。
かすがい市民文化財団は、地域の文化発信拠点として、先を見据えた事業を展開されており、またそれを実働させるための運営や広報の体制が整っていると感じています。
私が春日井に来て約1か月が経ち、財団情報誌「FORUM PRESS」の取材及び記事作成や、公演のフロント業務、子ども向けワークショップの準備や運営、展示会場設営など、様々な業務に関わらせていただいています。充実の日々で、1日があっという間に過ぎていきます。

子ども向けワークショップ:てのひらを使ったスタンプ。子どもたちは夢中で遊んでいました

市民美術展覧会:作品の受付や展示の作業を行いました
今回は、私が携わらせてもらった仕事の1つ「FORUM PRESS」についてお伝えいたします。
財団が2か月おきに発行している情報誌「FORUM PRESS」は、公演の見どころはもちろん、映画上映会のテーマにちなんだ漫画の紹介、地域のお店情報、春日井市内の学校の校歌を紹介するなど、バリエーション豊かな内容になっています。
また表紙の写真は春日井にまつわるもので、表紙をめくるとカメラマン直々の解説が載っていたりと、とても読み応えがあります。
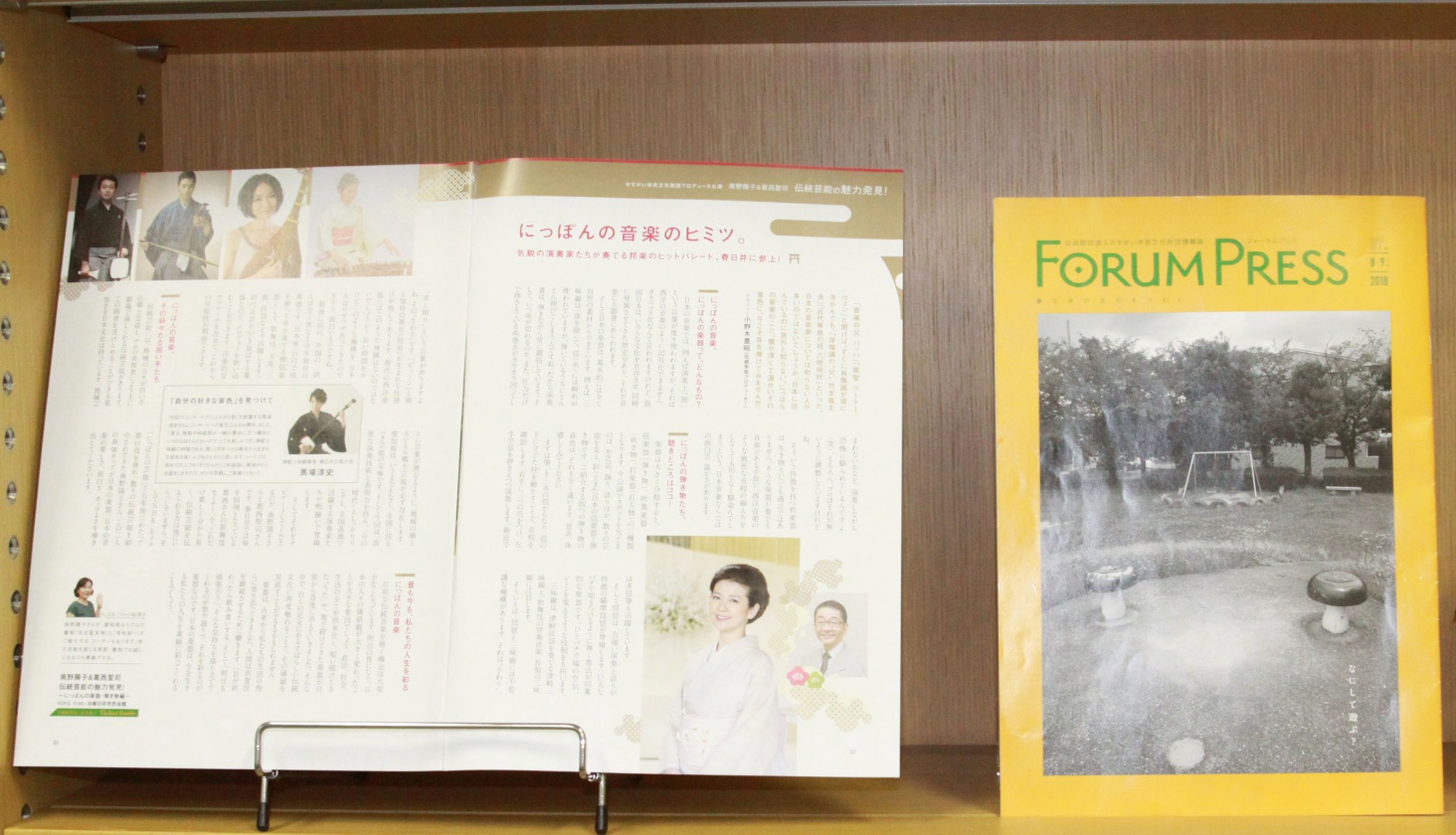
そんな情報誌ですから、当然こだわり抜いて作成されています。
私が書いた記事を確認してもらった時のことです。
作成した記事について、何故この内容を選んだのか、何故この言葉を選ぶのか、他にもっと良い言葉はないか、文章の順序を変えるとどうなるか等々、“愛のある”ご指摘に目から鱗でした。それぞれの記事に対しての掘り下げ方、向き合う姿勢がとても熱いんです。
その熱量は他のことでも同様らしく、打ち合わせ中にスタッフ同士で喧々諤々し、討論がヒートアップすることもしばしばあるそうです。良いものを作りたい、提供したいという気持ちがとても強いスタッフの皆さん。文化事業及び会館運営のプロが集まっています。ちなみに、スタッフの皆さんはとても親切で、いつも楽しそうに仕事をされています。
自分に厳しく、人にやさしい「(公財)かすがい市民文化財団」。
残りわずかですが、可能な限り学べるよう頑張りたいです。
【FORUM PRESSレポーター】西本喜美子写真展「みんなで遊ぼ、楽しかよ!」
「FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。
市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。
今回は、2018年5月30日(水)~6月10日(日)に開催された、
【西本喜美子写真展「みんなで遊ぼ、楽しかよ!」】を、8人がレポート!
FORUM PRESSvol.87にもレポートを掲載しています。Report295はコチラからPDFでお読みいただけます。

Report298【見て、撮って、楽しんで。】 たもとかんな
西本喜美子さんの写真展「みんなで遊ぼ、楽しかよ!」では、自撮り写真やデジタルアート、テーブルフォトなど107点が展示されました。パソコンを使って面白く加工したものや、着ぐるみを着て撮った自撮り写真などがあり、子どもから大人まで、たくさんの人がおとずれ、楽しんで見ていました。会場には写真を撮る時に使った、竹かごやほうきなどの道具がおいてあり、見にきた人も道具を使って写真を撮ることができるコーナーもありました。また、トークショーもあり、満席になりました。喜美子さんは「空想を浮かべながら作っています」「楽しく好きなことをやっていけばよいと思います」と語ってくださいました。トークショーには、長男の和民さんも登場。喜美子さんが写真をはじめたきっかけとなる写真講座「遊美塾」の先生でもある和民さんは「出会い、発見が大切です」と教えてくださいました。とても楽しかったです。私もたくさん写真を撮りたいです。
 Report299【写真は生きがい。楽しい!を発見。】 紀瑠美
Report299【写真は生きがい。楽しい!を発見。】 紀瑠美
ユーモラスな自撮り写真で人気の西本喜美子さんの写真展は、楽しかったです。自撮り写真57点、デジタルアート15点、デジタル処理なしで光などを工夫したテーブルフォト35点がコーナー別に展示されていて、見応えがありました。身の周りには、たくさんの「面白い」があると気づかされました。
作品の前で写真を撮ることができる自撮りコーナーでは、用意された小道具を使って撮影を楽しむ来場者の姿がありました。撮った写真を「ツイッター」に投稿すると、会場に写真を展示してもらえました。
6月2日には、喜美子さんのトークイベントがありました。喜美子さんは、トークイベント5分前まで会場で来場者と笑顔で交流し、トークイベント終了後にも昼食を手早くすませ、また会場にいらっしゃっていました。疲れるということはなくて、楽しいとのこと。写真については「面白い、みなさんやってみてください。なんでもできますので。難しいことは何もないですよ」と話していました。
 Report300【生き生きカメラマンは90歳】 こじまみつこ
Report300【生き生きカメラマンは90歳】 こじまみつこ
72歳でカメラを始めた西本さん。愉快な写真を撮りまくっています。
何事も「うまい・へた」はある。だけど「いい・わるい」はない。「自分流が一番大切」をモットーに。
自分で自分を撮るセルフポートレート。その中には、車と並んで笑顔でシルバーカーを走らせる西本さんに、運転手さんがびっくりしている写真も。「おばあちゃん、なんばしよっと!?」楽しい写真がいっぱいです。
デジタルアートは異世界への入り口。写真の中の不思議な目が私たちを見つめています。
雑貨や拾った物を使ったテーブルフォトでは、淡い色の背景に、おめかしする小物たちがかわいらしく撮られています。「みんなで遊ぼ 楽しかよ」と熊本弁で語りかける西本さん。西本さんの言葉は誰にでも何にでも、愛情いっぱいです。
2日のトークイベントの前後にギャラリーに現れた西本さんは、来場者に気さくに語りかけ、一緒に写真を撮り、握手をしていました。西本さんの手はふっくらと温かく、雑貨や小物たちに注ぐ優しい眼差しがそのまま手に表れているようでした。
Report301【「自分流」が一番大切】 中林由紀江
90歳のアマチュアカメラマン西本喜美子さんの写真展「みんなで遊ぼ、楽しかよ!」を観に行きました。通販カタログの表紙を飾ったり、SNSで評判のアマチュア写真家です。
72歳でカメラに初めて触れてから、持ち前の行動力で自宅に撮影スタジオを作られたそうです。「どうせ撮るなら、嫌われるよりも笑われた方がいい」という発想でセルフポートレートを撮られている喜美子さん。展示されているユーモラスな写真に足を止めて、思わず笑ってしまいました。一方、エッセイ付きのテーブルフォトは、セルフポートレートとは違い、やわらかい印象の素敵な作品です。そこに書いてある言葉も方言だからか、観る人の心にストレートに響いて、勇気をもらえるものでした。会場にお見えになったご本人は、お顔がつやつやで、生き生きとされたとても可愛いおばあちゃんでした。「何かを始める事に年齢は関係ない。人は何歳からでも始められる」という力強い言葉に、パワーをもらいました。
Report302【写真好きな家族に囲まれて】 和田卓夫
人生百年時代
八十代に咲かなければ九十代に咲けばよい
年を重ねても、なお美しさがのこる西本喜美子さん
90歳の西本喜美子さん、初めてカメラに触れたのは72歳とか。カメラ好きのご主人と息子さんに囲まれて、持ち前の進取の気鋭と行動力で、遅咲きながら、写真を自分の物にしていくストーリーが感じられた、素晴らしい写真展でした。
特に、「主人が買ってくれたカメラ 久しぶりにのぞいてみる
カメラの向こうにあるものが みんな私に話しかけてくる
きっと 頑張れって言ってくれてるんだね
そう ひとりじゃなかよ」
という言葉が添えられた、枯れた「ほおずき」の9つの房が群がる写真は、喜美子さんの気持ちを表しているようでした。
人生、趣味を持って活かして生きれば、幾つになっても、活躍していくことができます。高齢、少子化で人口減少の社会。これからの大きな変化を先取りした遅咲きのモデルの企画は、今からでも遅くないと考えさせられました。
Report303【写真は「頭で」撮る!】 ますだけいこ
ユーモアたっぷりの自撮り写真で、雑誌の表紙やCMに出演している写真家の西本喜美子さん。SNSでも話題とあって、トークイベントには男女問わず、年齢も様々な人たちが集まりました。
写真もユニークなら、その経歴もただ者ではない!?のですが、喜美子さんは「特別なことは何も・・・」と言わんばかりの淡々としたご様子。外見も、穏やかで優しそう。でも、内緒で試験を受けて、美容師から競輪選手になってしまうなんて、すごい行動力。「好きなことを楽しくどんどんやっていけばいい」というガッツは若いときからだったのですね。どれもかわいい写真作品の数々。喜美子さんは、「撮った写真はみなかわいい。たとえ動けなくなっても、天井やクモの巣を撮る」と写真への想いを語られました。
厳しい師でもある息子の和民さんによると、「『いいなあ』と自分の考えだけで撮っているから穴はあります。でも、見た瞬間に気持ちをつかめる写真を撮るから上手なんですよ」
これからも、写真で脳を活性化して、すてきな作品を撮ってくださいね。
Report304【小さな体から大きな発信】 澤田佳奈子
大きな拍手に迎えられて登場したのは、小柄な西本喜美子さん。この5月に90歳を迎え、SNSでも話題のおばあちゃん写真家です。首から掛けた「Nikon」のカメラを終始大事に抱える姿が印象的でした。180人ほど入る会場は、子どもから年配の男女で満席です。喜美子さんの発言やしぐさを見逃すまいとジッと熱い視線を送る観客たち。時にクスッと笑ったり、拍手を送ったりと、和やかムードでした。喜美子さんは、美容師、競輪選手などバラエティに富んだ経歴や、カメラ教室に通い始めたいきさつをお話してくださいました。72歳から始めたカメラの先生は息子の和民さん。「自分が撮りたいと思った物をどう表現するか、それに必要な事だけ教えました」そして、内に秘める好奇心・向上心・発想力・表現力が本領発揮、話題のセルフポートレートが生まれました。「楽しいですよ」とは、喜美子さんが何度も口にした言葉。人生何を始めるにも年齢は関係ない、興味を持ち楽しいと思えることが大切だなぁと、改めて感じました。
【FORUM PRESSレポーター】第2回ワンコインコンサート「Trio Primavera」
FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。
市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。
今回は、2018年6月1日(金)に開催された、
【第2回ワンコインコンサート「Trio Primavera」】をレポート!
FORUM PRESSvol.87にもレポートを掲載しています。Report297はコチラからPDFでお読みいただけます。

Report296【癒しの三重奏、豪華なひととき】 山田真穂
ワンコインコンサートの第2回は、名古屋芸術大学卒業生のフルート、オーボエ、ピアノによる「Trio Primavera」の公演でした。前半は『フィガロの結婚』から始まり、クラシック音楽を中心に展開。楽器紹介では、フルートの穴には硬貨が入らないこと、オーボエは円錐形なので音のバランスをとるのが難しいことなどの豆知識が面白かったです。前半の最後を飾ったのは、ピアノの蒔田さん編曲のオペラ『ラ・ボエーム』より抜粋。オペラ曲を管楽器の演奏で聴くのは新鮮であったと同時に、最後の場面で管楽器の2人が演奏しながら退場し、ピアノのみ残り、消灯するという演出も素敵でした。
後半は映画音楽が中心。特に『サウンド・オブ・ミュージック・メドレー』は、所々難しい和音を用いておしゃれにアレンジされており、普段と違った雰囲気で楽しめました。最後のアンコール『見上げてごらん夜の星を』では歌詞を口ずさみながら聴き入る方も多く、あたたかい雰囲気の中コンサートが締めくくられました。